中医学とは、中国の伝統医学であり、数千年の歴史を持つ医療体系です。
全体論的なアプローチに基づき、人体を一つの有機的な全体として捉え、バランスを保つことで健康を維持することを目指します。
中医学では、鍼灸や中薬、推拿、気功などの治療法が用いられ、患者の症状や体質に応じた診断が行われます。
陰陽五行説とは
東洋医学理論のベースにあるのが、「陰陽五行説」と呼ばれる思想です。
「陰陽論」と「五行説」の2つがいっしょになったものですが、どちらも自然や人体の観察から生まれた哲学的な思考法です。

陰陽論では、自然界のあらゆるものを「陰」と「陽」の、対立する2つの要素に分けて考えます。
陰と陽は相反する性質をもっているが、一方がどちらかを打ち負かしてしまうことのないように、常にバランスをとりあっています。
自然界では、夜は陰で、昼は陽、月は険㌻太陽は陽、水は陰で、火は陽とされます。
また、人体では、「五臓」が陰で、「六腑」が陽、背中が陽で、おなかが陰とされます。
こうした陰と陽の分類は絶対的なものではなく、比較する相手によって変化します。
たとえば、背中とくらべるとおなかは陰ですが、同じおなかでも上のほうは陽で、下のほうは陰となるといった具合です。
五行説では、自然界のさまざまな要素を「木」「火」「.t」「金」「水」の5つの要素である「五行」に分けて考えます。
これらの5つの要素には、それぞれ特徴的な性質があります。
木はまっすぐ上に伸びる性質、火は燃え上がる性質、土は生み育てる性質、金は変化・収縮させる性質、水は下に流れて潤いをあたえる性質があるとされます。
それぞれの性質によって、五行は、お互いに助け合ったり、牽制し合ったりしながら、全体のバランスを保っています。
五行が相互に助け合う関係を「相生」といい、牽制し合う関係を「相克」といいます。
人体の「五臓」の閲にも、こうした相生や相克の関係があり、五行説の考えかたは診断や治療にも生かされています。
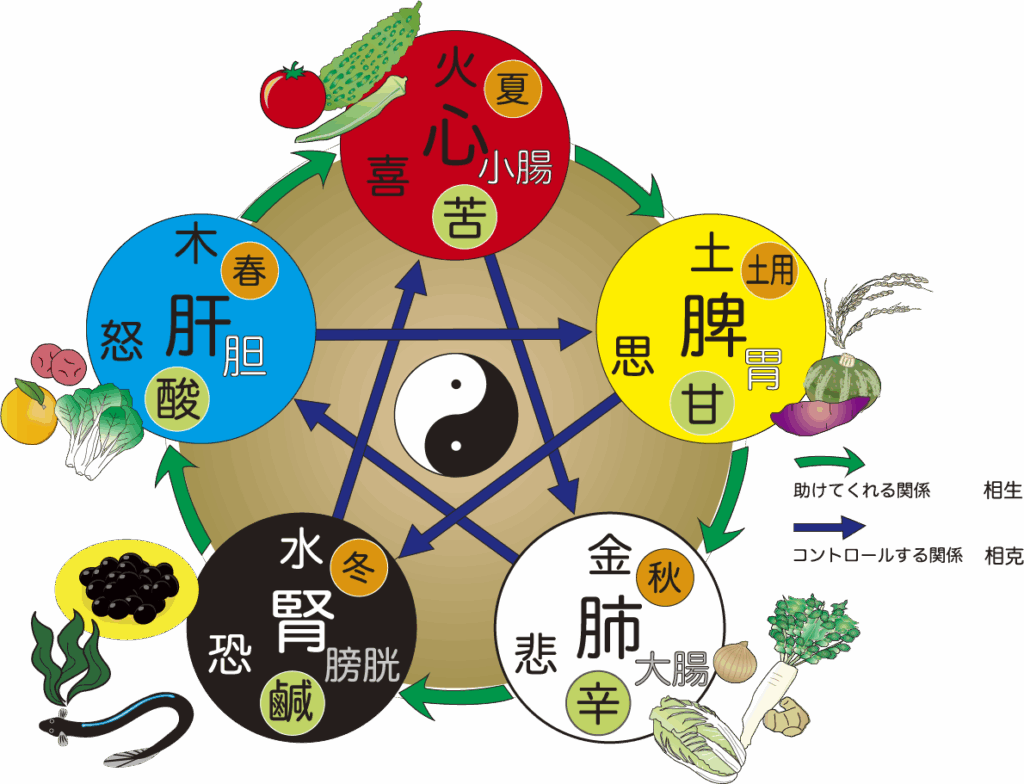
「天人合一」思想とは
東洋医学では、自然と人体は同じ要素をもっていると考え、自然界の現象を参考に体内のしくみや異常を想定します。
●人体と天地自然は同じ要素をもっている

人も自然の一部と考える東洋.医学では、自然を大宇宙、人を小宇宙として、大宇宙の法則は小宇宙にも働くと考えています。
たとえば、自然界では5つの季節の変化により、風・暑火・湿・燥・寒という気候が生まれ、これが激しいと人体を吉する病邪(体外に発生するため外邪とも呼ばれる)となります。
一方、生活習慣の乱れによって体内に起こる変化のことは、内傷五邪と呼んでいます。
外邪と内傷五邪は対応しており、願似した特徴の病状を起こします。
こうした自然の変化と人体との相関関係を「天人合一」といい、「陰陽論」や「五行論」とともに、中医学の考え方の原点となっています。
実証と虚証とは
病気の原因になっているものと、体の抵抗力の源である正気、そのせめぎあいの結果を説明している。
●病気の原因と体の防御力とのせめぎあい
中医学の診断では、病気の性質や病状をあらわすときに、「実証」と「虚証」という相対する名称がよく使われます。
人が病気になるのは、発病因子である「病邪(邪気)」と体の抵抗力の源である「正気」とのせめぎあいの結果、病邪が勝ったときです。
実証・虚証という名称は、発病の要因が病邪の側にあるのか、正気の側にあるのかを判断して使われます。
実証と呼ばれるのは、体の防御力は充分なのに、病邪の勢いが強すぎる(「実している」という)ために病気になってしまった場合です。
逆に、虚証と呼ばれるのは、体の抵抗力が低下している「虚している」という)ために、病邪はそれほど強くないのに病気になってしまった場合です。
たとえば、感染力の強いウイルス性のかぜが流行して、ふだんは元気な人でもそれにかかってしまうという場合は、実証です。
しかし、ふつうの人ならかぜを引かないようなちょっとしたクーラーの冷気でも、正気が虚しているため、すぐにかぜを引いてしまうという場合は、虚証といえます。
同じかぜでも、虚証か実証かによって病状は異なり、当然、治療法も違ってきます。
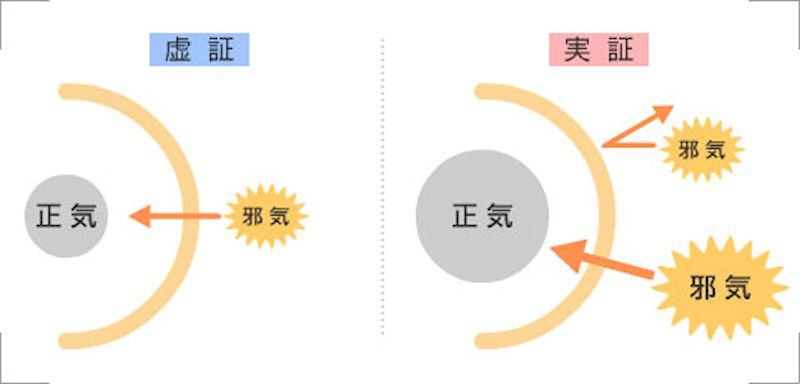
●がっちり型=実証 やせ型=虚証というのは正確ではない
「がっちり体型で体力のある人は実証で、やせ型で虚弱体質の人は虚証」と考える人も多いようだが、これはあまり正確ではないです。
たとえば、がっちり体型で、ふだんは体力のある人でも、疲労が原因で発病すれば、その病気に関しては、虚証ということになります。
つまり、実証・虚証というのは、あくまでも治したい病気を分析した結果の判断であって、その治したい病気は、かならずしも、ふだんの体質とマッチするとは限らないのです。
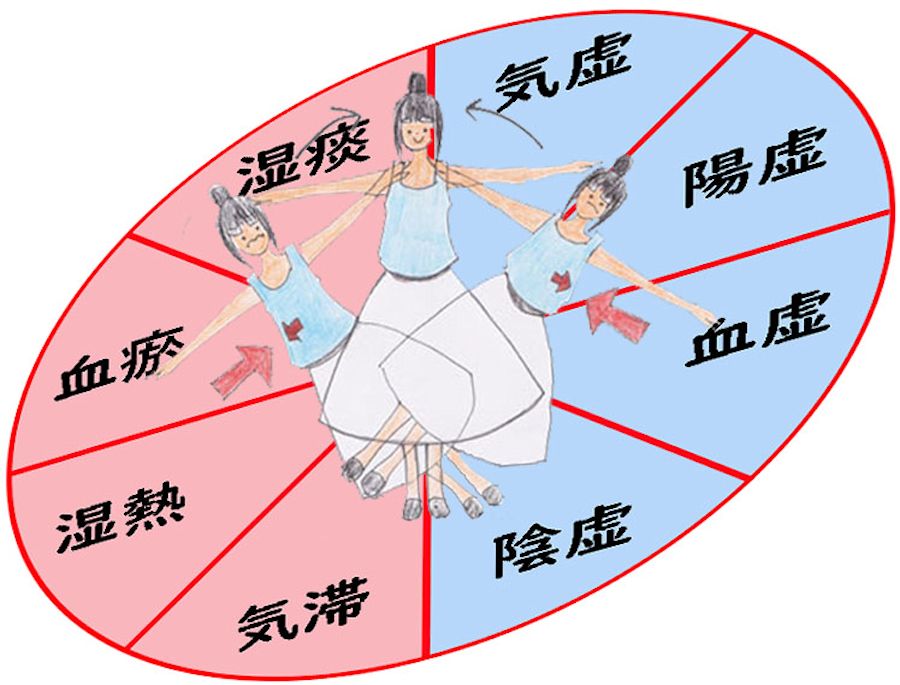
中医学の健康状態とは
身体の抵抗力の源である正気が充実してこそ、病気にかかりにくい身体の状態を維持することができます。
●健康状態の決め手は、正気の充実
現代医学(現代的な西洋医学)では、血液検沓などの値が正常範囲内におさまっていれば、健康だとされます。
しかし、実際には、正常の範囲でも症状をうったえる人もいるし、また、正常値を上わっていても平気な人もいます。
東洋医学では、検査の植は参考にするが、それを中心にして、病気を判断することはないです。
東洋医学的に健康を考えるとき、重要な指標になるのは、免疫力や抵抗力の源とされる「正気」の充実です。
そのためには、
①「気」「血」「津液」の補充や代「耐が1’分であること、
②寸五臓六蹄」の働きが順調であること、
③「陰腸」のバランスがとれていることが条件になます。
●気・血・津液が正気を生み出す
気・血・津液は、人身体をつくったり、活動させたりするための基礎的な物質とされています。
正気も気・血・津液から生み出されるため、これらが不足していたり、あるいは代.討が悪かったりすると、病気になりやすくなります。
●五臓六腑の働き
気・血・津液をつくり、その補充や代謝を行うのは五臓六腑であります。
六腑が順調に働けば、気・血・津液は充実し、それによって正気も充実します。
●陰陽のバランス
東洋医学のベースには、対になる2つのものを「陰」と「陽」に分類して考える「陰剛論」があります。
人の身体では、背中側が陽、おなか側が陰口「五臓」が陰、「六腑」が陽。気・血・津液では、気が陽、血と津液が陰とされます。
陰陽論によると、陰と陽の間にはいくつかの法則があります。
陰陽のバランスが乱れによってその法則がくずれ、それが気・血・津液にまで及ぶと、正気は充実できずに、病気になりやすくなります。
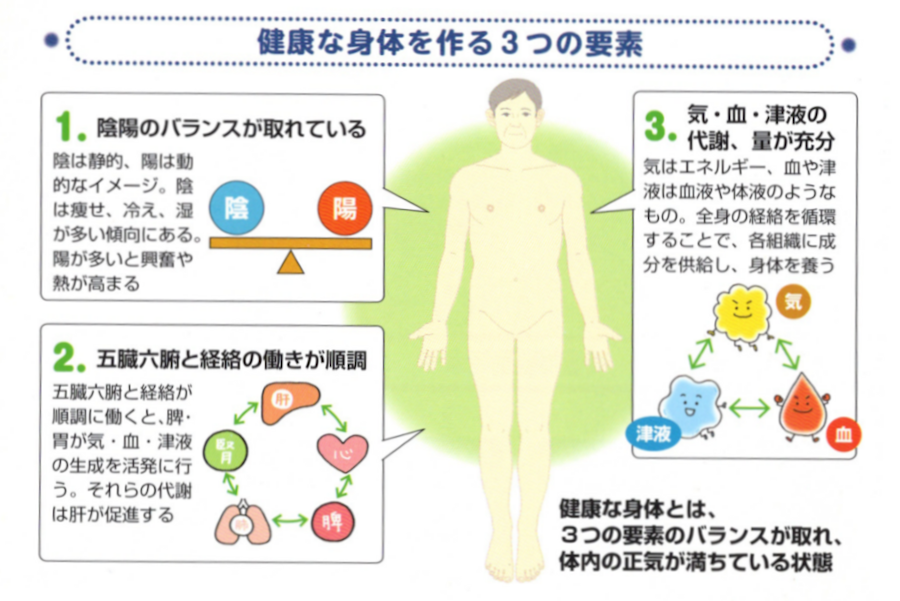
鍼灸・治療法
東洋医学の治療法には、大きく分けて施術をする「鐵灸・按摩」と薬を処方する「漢方」があります。
症状に合わせてこれらを別々に用いたり、併せて用いて治療します。
●鍼(はり)
細い鐵を刺してツポに働きかける。
非常に細い鐵をツボに刺して刺激を与え.ツボから体を流れる「気」に働きかけて、体内の患部や不調の原因となっている部位の調子を整えます。
身体中を巡る纏鱈により、たとえば足のツボに刺激を与えることで、頭の症状を治療することもできる。
治療には注射針の6分の1から2分の1という細い鐵(はり)が用いられるため、ほとんど痛みは感じないです。
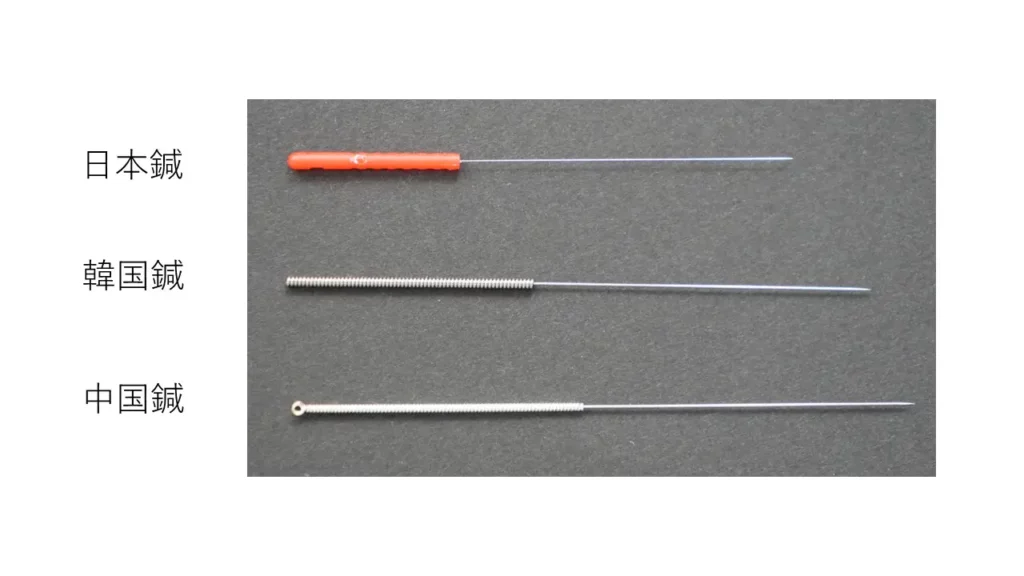
●灸(きゅう)
もぐさに火をつけ、ツボを温める。
ツボに刺激を与えて体内の不調を正す考え方は鍍と同じですが、ツボに乗せたもぐさに火をつけて温める灸は.冷えの症状にとくに効果があります。
灸をツボの1点にすえるだけで、全身の血行をよくし、温めることができます。
ツボに乗せるもぐさの大きさや固さ、燃やす時間などは治療の目的に応じて変わります。
●按摩(あんま)
ツボや経絡を手のみで刺激する。
押す、もむ、さする、なでるなどの手技を使い分けながら、ツボとともに「経絡」を刺激する療法。身体の中心から外に向かって行うのが特徴です。
経絡やツボを手で押す按摩は.不調の緩和だけでなく、リラクゼーション効果もあります。
按摩と同じようにツボを指で押して刺激する「指圧」は日本で独自に発達した手技療法です。

